アメリカ軍で最も強い狙撃手と呼ばれた、クリス・カイルの自叙伝を実写化したドラマ。アメリカ海軍特殊部隊ネイビーシールズ所属のスナイパーであった彼が、イラク戦争で数々の戦果を挙げながらも心に傷を負っていくさまを見つめる。メガホンを取るのは、『ミリオンダラー・ベイビー』などのクリント・イーストウッド。『世界にひとつのプレイブック』などのブラッドリー・クーパーが主演を務め、プロデューサーとしても名を連ねている。戦争とは何かを問うテーマに加え、壮絶な戦闘描写も見もの。
あらすじ:イラク戦争に出征した、アメリカ海軍特殊部隊ネイビーシールズの隊員クリス・カイル(ブラッドリー・クーパー)。スナイパーである彼は、「誰一人残さない」というネイビーシールズのモットーに従うようにして仲間たちを徹底的に援護する。人並み外れた狙撃の精度からレジェンドと称されるが、その一方で反乱軍に賞金を懸けられてしまう。故郷に残した家族を思いながら、スコープをのぞき、引き金を引き、敵の命を奪っていくクリス。4回にわたってイラクに送られた彼は、心に深い傷を負ってしまう。
![]()
<感想>冒頭にて、建物の屋上で銃をかまえる米軍スナイパーの照準器が、向かい側の建物のから出てくる母親らしき女と少年をとらえる。「判断に任せる」という命令に、スナイパーは撃つのか撃たないのか、息詰まる数秒間の末に、不意に画面が反転する。それは、狙撃兵の少年時代に父親と鹿狩りに行ったシーンが映し出される。父親が言うのは、人間には「羊と狼に番犬」という種類がある。羊は虐められるし、番犬として家族を守るために狼と闘うと言うのだとも。
大きくなったクリスは、アメリカ海軍特殊部隊ネイビーシールズの隊員となるために、厳しい訓練を受け、その後結婚式と子供の誕生といった彼の半生の記憶が走馬灯のように次々トモンタージュされる。そして、イラクへと派遣されるクリスが冒頭のシーンに戻る。少年は手にロケット型手榴弾を持ち米軍部隊の方へ向かって走っていく。その少年をクリスが捉えて射殺する。
![]()
人は死の瞬間に一生の記憶を思い出すと言うが、それなら同じことが人の命を奪う瞬間に起こっても不思議ではない。殺すにせよ、殺されるにせよ、死の瞬間とは、誰にも経験できない不可知であり、人の全生涯を極限まで凝縮したぬきさしならぬ一点であるだろう。
引き金を引くのか、引かないのか、その時、空間は銃口と標的とを結ぶ一本の線へと。クリスが屋上から下の標的を狙うスナイパーであると同時に、そんな彼をさらに上から狙う謎のシリア人スナイパーを登場させることで、彼自身もまたいつ弾が上から降ってくるか分からない立場に置かれる。照準器ごしに人の命を弄ぶ、彼自身がそうであるスナイパーと言う存在を排除すべく、彼はもう一人の自分というべきスナイパーを追って上へと、階段を上っていく。この抜きつ抜かれつが、気が付けばいつものイーストウッド映画のスリル感なのですね。
![]()
とにかく主人公の狙撃兵クリスの腕は超一流で、1920mもの先にいる、敵である五輪で金メダルの保持者のシリア人スナイパーを、照準器の中で標的の身体に十字の印がピタリと重なる瞬間、敵を肉眼で捉え射撃するのだ。これが見事に敵の狙撃兵に命中するという快挙を遂げている。だからというわけでもないが、主人公クリスを英雄化していると思われるのも頷ける。まるで英雄なのか、悪人かで描いているようにも取られる。
![]()
それは、9.11後に間違った理由で戦争を開始したアメリカが、その後ブッシュ政権への支持、不支持でまっぷたつに分かれたことをも彷彿とさせるものでもある。ですが、この映画は、イラク戦争がどうのとかではなく、一人の狙撃兵クリスの葛藤を描いているのだ。ですが、ここで描かれている兵士の葛藤というのは、例えば少年や女性を目の前にしても、それをアメリカのために撃ち殺さなければいけない、という葛藤だったりする。
最終的に最も印象に残るのは、ロケットランチャーを手にした少年を狙撃するかしないかの瀬戸際で、クリスが神に祈る手に汗を握るシーンではない。迫りくる巨大な砂嵐の中で生きるか死ぬかの攻防戦を繰り広げるシーンでもない。
こういう戦地のシーンでは、80代半ばのイーストウッド監督が撮ったものとは思えないほど、本当に骨太で妥協のない肉体、精神とともにタフで研ぎ澄まされていなければ、形にできない映像ばかりである。
![]()
だが、本当に重要なのはクリスが戦地に行って帰って来る度に、変容していく家庭のシーンなのである。戦地で陰惨な光景を目の当たりにした彼は、家に帰っても近所から聞こえる工具の音にもビクつき、バーベキュー・パーティで可愛がっていた犬にも子供にじゃれ付いているだけなのに、子供を犬が襲い掛かっていると判断して恐怖の顔をして犬を殺そうとするのだ。
それは戦争のトラウマといった単純なものではない。戦地から帰ってきても、クリスの中では戦争は続いていて、特に彼ほどにその能力が戦地で、影響力を持つ人になってしまうと、家庭で平穏に日常生活を送っていることが、実際に戦地にいる人たちが生きるか死ぬかを左右してしまう。かと言って、永遠に戦地で米軍部隊を守る狙撃兵を続けることは、精神状態が不可能なのだ。
だから、クリスにとっては、戦争をしているアメリカという国に属している限り、戦地も帰国しての家庭もないのだ。何処に居ても、たとえ兵士を辞めても、彼の精神状態は殺し合いの螺旋に巻き込まれたまま逃れることが出来ないのである。
![]()
だから、戦地に行ったことのない家族には、本当の意味でそのことを理解することは出来ないと思う。帰って来て、家庭でのシーンでは、戦地のシーン以上に悲劇性が強い。イラク戦争の映画というと、ジェレミー・レナー演じる兵士「ハート・ロッカー」「ゼロ・ダーク・サーティ」でもそのような描写が描かれて、何度も戦地へと行く兵士の心情が描かれていた。
ラストのエンドクレジットの後半で、あまりにもさらっと無音で字幕スーパーが流れる結末こそが、もっとも大事な部分なのではないかと。160人の蛮人を射殺したクリス・カイルが、国民的英雄として葬送される映像に、遺体搬送車が通行する道路沿いには、無数の人々が押し寄せ彼を葬送している。
映画の中の銃声や地響きや物音などが印象的だっただけに、この無音は対照的でした。しかも、その前にクリスの短い人生が暗示されるだけに、観る側が胸につまされます。それは、結局戦争に勝者は存在しないということが。その末端で、正義のために葛藤した兵士たちこそが、その犠牲になるという残酷な事実を知らせている。
2015年劇場鑑賞作品・・・32![]() 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング
あらすじ:イラク戦争に出征した、アメリカ海軍特殊部隊ネイビーシールズの隊員クリス・カイル(ブラッドリー・クーパー)。スナイパーである彼は、「誰一人残さない」というネイビーシールズのモットーに従うようにして仲間たちを徹底的に援護する。人並み外れた狙撃の精度からレジェンドと称されるが、その一方で反乱軍に賞金を懸けられてしまう。故郷に残した家族を思いながら、スコープをのぞき、引き金を引き、敵の命を奪っていくクリス。4回にわたってイラクに送られた彼は、心に深い傷を負ってしまう。

<感想>冒頭にて、建物の屋上で銃をかまえる米軍スナイパーの照準器が、向かい側の建物のから出てくる母親らしき女と少年をとらえる。「判断に任せる」という命令に、スナイパーは撃つのか撃たないのか、息詰まる数秒間の末に、不意に画面が反転する。それは、狙撃兵の少年時代に父親と鹿狩りに行ったシーンが映し出される。父親が言うのは、人間には「羊と狼に番犬」という種類がある。羊は虐められるし、番犬として家族を守るために狼と闘うと言うのだとも。
大きくなったクリスは、アメリカ海軍特殊部隊ネイビーシールズの隊員となるために、厳しい訓練を受け、その後結婚式と子供の誕生といった彼の半生の記憶が走馬灯のように次々トモンタージュされる。そして、イラクへと派遣されるクリスが冒頭のシーンに戻る。少年は手にロケット型手榴弾を持ち米軍部隊の方へ向かって走っていく。その少年をクリスが捉えて射殺する。

人は死の瞬間に一生の記憶を思い出すと言うが、それなら同じことが人の命を奪う瞬間に起こっても不思議ではない。殺すにせよ、殺されるにせよ、死の瞬間とは、誰にも経験できない不可知であり、人の全生涯を極限まで凝縮したぬきさしならぬ一点であるだろう。
引き金を引くのか、引かないのか、その時、空間は銃口と標的とを結ぶ一本の線へと。クリスが屋上から下の標的を狙うスナイパーであると同時に、そんな彼をさらに上から狙う謎のシリア人スナイパーを登場させることで、彼自身もまたいつ弾が上から降ってくるか分からない立場に置かれる。照準器ごしに人の命を弄ぶ、彼自身がそうであるスナイパーと言う存在を排除すべく、彼はもう一人の自分というべきスナイパーを追って上へと、階段を上っていく。この抜きつ抜かれつが、気が付けばいつものイーストウッド映画のスリル感なのですね。

とにかく主人公の狙撃兵クリスの腕は超一流で、1920mもの先にいる、敵である五輪で金メダルの保持者のシリア人スナイパーを、照準器の中で標的の身体に十字の印がピタリと重なる瞬間、敵を肉眼で捉え射撃するのだ。これが見事に敵の狙撃兵に命中するという快挙を遂げている。だからというわけでもないが、主人公クリスを英雄化していると思われるのも頷ける。まるで英雄なのか、悪人かで描いているようにも取られる。

それは、9.11後に間違った理由で戦争を開始したアメリカが、その後ブッシュ政権への支持、不支持でまっぷたつに分かれたことをも彷彿とさせるものでもある。ですが、この映画は、イラク戦争がどうのとかではなく、一人の狙撃兵クリスの葛藤を描いているのだ。ですが、ここで描かれている兵士の葛藤というのは、例えば少年や女性を目の前にしても、それをアメリカのために撃ち殺さなければいけない、という葛藤だったりする。
最終的に最も印象に残るのは、ロケットランチャーを手にした少年を狙撃するかしないかの瀬戸際で、クリスが神に祈る手に汗を握るシーンではない。迫りくる巨大な砂嵐の中で生きるか死ぬかの攻防戦を繰り広げるシーンでもない。
こういう戦地のシーンでは、80代半ばのイーストウッド監督が撮ったものとは思えないほど、本当に骨太で妥協のない肉体、精神とともにタフで研ぎ澄まされていなければ、形にできない映像ばかりである。

だが、本当に重要なのはクリスが戦地に行って帰って来る度に、変容していく家庭のシーンなのである。戦地で陰惨な光景を目の当たりにした彼は、家に帰っても近所から聞こえる工具の音にもビクつき、バーベキュー・パーティで可愛がっていた犬にも子供にじゃれ付いているだけなのに、子供を犬が襲い掛かっていると判断して恐怖の顔をして犬を殺そうとするのだ。
それは戦争のトラウマといった単純なものではない。戦地から帰ってきても、クリスの中では戦争は続いていて、特に彼ほどにその能力が戦地で、影響力を持つ人になってしまうと、家庭で平穏に日常生活を送っていることが、実際に戦地にいる人たちが生きるか死ぬかを左右してしまう。かと言って、永遠に戦地で米軍部隊を守る狙撃兵を続けることは、精神状態が不可能なのだ。
だから、クリスにとっては、戦争をしているアメリカという国に属している限り、戦地も帰国しての家庭もないのだ。何処に居ても、たとえ兵士を辞めても、彼の精神状態は殺し合いの螺旋に巻き込まれたまま逃れることが出来ないのである。

だから、戦地に行ったことのない家族には、本当の意味でそのことを理解することは出来ないと思う。帰って来て、家庭でのシーンでは、戦地のシーン以上に悲劇性が強い。イラク戦争の映画というと、ジェレミー・レナー演じる兵士「ハート・ロッカー」「ゼロ・ダーク・サーティ」でもそのような描写が描かれて、何度も戦地へと行く兵士の心情が描かれていた。
ラストのエンドクレジットの後半で、あまりにもさらっと無音で字幕スーパーが流れる結末こそが、もっとも大事な部分なのではないかと。160人の蛮人を射殺したクリス・カイルが、国民的英雄として葬送される映像に、遺体搬送車が通行する道路沿いには、無数の人々が押し寄せ彼を葬送している。
映画の中の銃声や地響きや物音などが印象的だっただけに、この無音は対照的でした。しかも、その前にクリスの短い人生が暗示されるだけに、観る側が胸につまされます。それは、結局戦争に勝者は存在しないということが。その末端で、正義のために葛藤した兵士たちこそが、その犠牲になるという残酷な事実を知らせている。
2015年劇場鑑賞作品・・・32
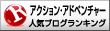 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング