旧ソ連ウクライナのチェルノブイリ原発事故が起きたのは、1986年4月26日深夜である。事故からすでに25年以上経っている。
![]()
テレビのドキュメンタリー番組や報道写真では度々見聞きしてきたが、実際に事故後の立ち入り制限区域内で撮った劇映画を見るのは初めてである。それもそのはず、事故後は規制が厳しく長く撮影許可が下りることがなかったのだから。
それを敢行したのがイスラエル出身の女性監督ミハル・ボガニム。1986年4月26日に起きた原発事故のドキュメンタリーではなく、当時そこに住んでいた人々を描く劇映画に仕立ててある。主人公のアーニャにオルガ・キュレンコが自ら熱望して挑んでいる。
あらすじ:1986年4月26日、チェルノブイリの隣村プリピャチで、アーニャとピョートルは結婚式を挙げる。しかし、幸せの絶頂の日であるはずのこの日、消防士のピョートルは「山火事の消火活動」という名目でパーティ中に駆り出され、2度と戻ることはなかった。10年後、観光名所となった廃墟の街をツアーガイドするアーニャ、事故当時に原発技師の父と生き別れとなった青年バレリー、事故後も頑なに自宅を離れず、汚染された土地を耕し続けた森林管理人のニコライという3人を通し、失われた故郷に心を置き去りにしたまま、現実と向かい合う人々の姿を映し出す。
![]()
<感想>前から観たかったので、やっとミニシアターで上映してくれて良かった。2年前の福島原発事故を振り返って。平穏な日常に、突然起きた史上最悪の事故。突如の暗転、事故の兆候は動物の異様な騒ぎや急に枯れる木々、川に浮かんだ魚の死体によって示される。空が墨汁を流したようで、何かが途方もなく大きな力が過ぎ去った後の、ただならぬ気配が感じる。真っ白い花嫁の衣装に容赦なく降り注ぐ放射能の黒い雨。ウェディングケーキが黒ずんだ雨でグショグショだ。肉もパンも卵もみな汚れてしまった。夜は星とともにオーロラのように燃えている。
![]()
やがて強制退去命令が下され、人々は何も教えられないまま私物の持ち出しを禁じられ、十数万人が故郷から永遠に離れることになったのである。
この恐ろしい描写から始まる被災地の記録から浮かび上がるのは、人々の絶望と哀しみである。それは放射能に対する恐怖や怒りというよりは、自分の生まれ育った土地への立ち入りを制限されたことに対する喪失感といったらいいのか。
事故当日に結婚式を挙げたアーニャの夫は、そのまま事故処理に駆り出されたまま帰らぬ人となった。夫の突然の死を告げられたアーニャは、搬送先となったモスクワに向かうバスを探すが、バス停前の壁にレーニンの有名なスローガン「共産主義は、ソビエトの権力と全国の電化」が掲げられていた。だが、その結末は、放射能の雨と故郷の喪失であった。
![]()
10年後、アーニャはツアーガイドとしてプリピャチに留まり、ガイドをすることで事故を語り続けている。原発技師のアレクセイは事故を隠した罪悪感から精神状態が狂い、故郷を見失ったまま放浪の旅を続ける。アレクセイは死んだと教えられた息子は、生きている父親を探しプリピャチに戻ってくる。
この映画はチェルノブイリのゾーン、立ち入り制限区域で撮影された貴重な映像。プリピャチは原子炉から3キロ、至近距離に建設された発電所の従業員居住地として作られた原発都市である。事故前は原発従業員など約5万人が居住していた。緑豊かな川に面して、高層住宅、大病院、学校、映画館、音楽堂、市民プール、遊園地など様々な施設があったが、死の灰の直撃でゴーストタウンと化した。病院には共産党大会のポスターが貼られ、学校にはレーニンを讃える教科書が散らばる。1991年に崩壊した“ソ連”が化石のようにそのまま残っていた。
![]()
過去は戻らない。しかし失われた過去は一層強く人々を拘束し続け、逃れようとしても逃れられない過去を、彼らは記憶しつづけようとしている。事故を語り記録を残し、壁に文字を刻むことで忘却に抵抗する。
ツアーバスの車窓から何度もカメラは廃墟と化した街を映す。それを眺めるアーニャの眼差し、その廃墟のなかを彷徨うアレクセイの息子。すでに野生化した動物たちが林を疾走し、中央アジアからの難民が無人化した家を不法占拠して住んでいる。せつなく圧倒されるシーンだ。もう帰れる場所がないのに、喪なわれた街から離れられない。福島原発事故からわずか2年で、事故を忘れるようとしているかに見える私たちへの警告のようにもとれた。
2013年劇場鑑賞作品・・・68![]() 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキングへ
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキングへ

テレビのドキュメンタリー番組や報道写真では度々見聞きしてきたが、実際に事故後の立ち入り制限区域内で撮った劇映画を見るのは初めてである。それもそのはず、事故後は規制が厳しく長く撮影許可が下りることがなかったのだから。
それを敢行したのがイスラエル出身の女性監督ミハル・ボガニム。1986年4月26日に起きた原発事故のドキュメンタリーではなく、当時そこに住んでいた人々を描く劇映画に仕立ててある。主人公のアーニャにオルガ・キュレンコが自ら熱望して挑んでいる。
あらすじ:1986年4月26日、チェルノブイリの隣村プリピャチで、アーニャとピョートルは結婚式を挙げる。しかし、幸せの絶頂の日であるはずのこの日、消防士のピョートルは「山火事の消火活動」という名目でパーティ中に駆り出され、2度と戻ることはなかった。10年後、観光名所となった廃墟の街をツアーガイドするアーニャ、事故当時に原発技師の父と生き別れとなった青年バレリー、事故後も頑なに自宅を離れず、汚染された土地を耕し続けた森林管理人のニコライという3人を通し、失われた故郷に心を置き去りにしたまま、現実と向かい合う人々の姿を映し出す。

<感想>前から観たかったので、やっとミニシアターで上映してくれて良かった。2年前の福島原発事故を振り返って。平穏な日常に、突然起きた史上最悪の事故。突如の暗転、事故の兆候は動物の異様な騒ぎや急に枯れる木々、川に浮かんだ魚の死体によって示される。空が墨汁を流したようで、何かが途方もなく大きな力が過ぎ去った後の、ただならぬ気配が感じる。真っ白い花嫁の衣装に容赦なく降り注ぐ放射能の黒い雨。ウェディングケーキが黒ずんだ雨でグショグショだ。肉もパンも卵もみな汚れてしまった。夜は星とともにオーロラのように燃えている。

やがて強制退去命令が下され、人々は何も教えられないまま私物の持ち出しを禁じられ、十数万人が故郷から永遠に離れることになったのである。
この恐ろしい描写から始まる被災地の記録から浮かび上がるのは、人々の絶望と哀しみである。それは放射能に対する恐怖や怒りというよりは、自分の生まれ育った土地への立ち入りを制限されたことに対する喪失感といったらいいのか。
事故当日に結婚式を挙げたアーニャの夫は、そのまま事故処理に駆り出されたまま帰らぬ人となった。夫の突然の死を告げられたアーニャは、搬送先となったモスクワに向かうバスを探すが、バス停前の壁にレーニンの有名なスローガン「共産主義は、ソビエトの権力と全国の電化」が掲げられていた。だが、その結末は、放射能の雨と故郷の喪失であった。

10年後、アーニャはツアーガイドとしてプリピャチに留まり、ガイドをすることで事故を語り続けている。原発技師のアレクセイは事故を隠した罪悪感から精神状態が狂い、故郷を見失ったまま放浪の旅を続ける。アレクセイは死んだと教えられた息子は、生きている父親を探しプリピャチに戻ってくる。
この映画はチェルノブイリのゾーン、立ち入り制限区域で撮影された貴重な映像。プリピャチは原子炉から3キロ、至近距離に建設された発電所の従業員居住地として作られた原発都市である。事故前は原発従業員など約5万人が居住していた。緑豊かな川に面して、高層住宅、大病院、学校、映画館、音楽堂、市民プール、遊園地など様々な施設があったが、死の灰の直撃でゴーストタウンと化した。病院には共産党大会のポスターが貼られ、学校にはレーニンを讃える教科書が散らばる。1991年に崩壊した“ソ連”が化石のようにそのまま残っていた。

過去は戻らない。しかし失われた過去は一層強く人々を拘束し続け、逃れようとしても逃れられない過去を、彼らは記憶しつづけようとしている。事故を語り記録を残し、壁に文字を刻むことで忘却に抵抗する。
ツアーバスの車窓から何度もカメラは廃墟と化した街を映す。それを眺めるアーニャの眼差し、その廃墟のなかを彷徨うアレクセイの息子。すでに野生化した動物たちが林を疾走し、中央アジアからの難民が無人化した家を不法占拠して住んでいる。せつなく圧倒されるシーンだ。もう帰れる場所がないのに、喪なわれた街から離れられない。福島原発事故からわずか2年で、事故を忘れるようとしているかに見える私たちへの警告のようにもとれた。
2013年劇場鑑賞作品・・・68
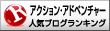 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキングへ
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキングへ