目の前で家族を亡くした一家が少しずつ再生していく様子を、『アンチクライスト』などのシャルロット・ゲンズブール主演を務めたヒューマン・ドラマ。夫亡き後、人生の目的を見いだせない母と、父親の魂が宿る大きな木に話し掛ける幼い娘を中心に、母娘、息子たちが共に生きていこうとする姿を描き出す。メガホンを取るのは、『やさしい嘘』のジュリー・ベルトゥチェリ。切ないストーリーにユーモアを交え、爽やかな感動を与えてくれる。
![]()
<感想>オーストラリアの力強い大自然の中、大きなイチジクの木に守られるかのように穏やかに暮らす一家。父と母と4人の子供たちの平和な暮らし。自然と人間が織りなす大きなドラマを予感させる舞台設定である。
しかし、父親のピーターが長期間にわたる仕事が終わり、が待つ自宅に戻る途中、心臓発作が原因でこの世を去ってしまう。残された妻のドーンは子どもたちを抱え、この先どうやって生きていけばいいのかわからない状態に陥っていた。そんなある日、8歳の娘シモーンが庭の大きなイチジクの木に父が宿っているのではないかと感じ、木と対話していることを知る。そんな時、新しい恋をする母親と対立するようになる。
![]()
この作品「パパの木」は、ジュリー・ベルトゥチェリにとっては「やさしい嘘」に続く長篇監督2作目。前作同様に、喪の作業が大きな柱になり、時にはユーモアを交えながら、母と娘が大自然と共に、愛する人の死を昇華していく姿が描かれていく。事実、これは、自然の力と人間の悲劇と再生と、ファンタジーと寓話に満ちた巧妙な作品になっている。撮影は見事だし、演技も充実している。わけても8歳の娘を演じるモーガナ・デイヴィーズが、あまりにも演技が達者で、母親役のシャルロット・ゲンズブールを食っているのが印象的だ。
![]()
この映画は、ジュディ・パシコーの小説が元になっているが、本作は原作よりもシャルロット・ゲンズブール演じるドーンの心理に重きが置かれているようだ。だが、この作品の中では幼い娘が父親は木の中で生きていると思いながら、父を失くした悲しみをやわらげ、そしてだんだんと父への執着を断ち切って行く。だからというわけでないが、シモーヌは一度も神の名を口にしない。今までの幾多の映画で描かれたように、神に父の復活を祈りはしない。この家族は特別な信仰を持たないという前提であったのだろう。神というものは大人が子供に教え込む存在であり、小さな子供が本能的に感じるものではないと思うから。シモーンには、神の存在より父親との交信の方が重要だったに違いない。
![]()
ですが、この木に父親が宿っていると信じることも一つの信仰だと思います。
木の精と家族の対話、彼らはそこに今は亡き父親の魂を感じ取り、日ごと、夜ごとに自分の悩みを打ち明けるのだ。
その思いが強すぎることは危険をはらんでいることも。その木がある限り父親の死を受け入れられることが出来ないのでは。死んだ人というのは、目に見えないけれども、生前以上に存在感を増すこともあるわけで、心の中に居続ける、というのは詩的だと思いますね。確か、邦画でも「桜、ふたたび加奈子」で、生まれ変わりを信じることに投影して描いていた。
![]()
木下の斜面の住居と共に、充実した画面が出現する。その存在感に負けない俳優たちも偉い。父の不在をめぐる母と娘の葛藤。母が新たな男性に近づこうとするときに、響き渡るバッハの「ヨハネ受難曲」。それはキリストの肌着の処分をクジで決めようとする兵士たちの戯れ画のようなフーガである。
ここで木がどういう手を打ってくるかが観る側の予想を超えて、嵐の夜に大音響と共に、木が倒壊するシーンに込められた深い思いには、母親のドーンも心動かされたようで。
一家が大型トラックで、トレーラーの荷台に平屋の家屋を載せて、オーストラリアの大地を移動するラストに、妙な感動を覚えた。土台から家ごと引っ越すこのカットに、どこで何が起きても家族が一体となって生きて行こうとする姿が見られる。「モーガナちゃん、ガンバレ」と、ついエールを送りたくなる自立と共生の映画ですね。
2013年劇場鑑賞作品・・・247![]() 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング

<感想>オーストラリアの力強い大自然の中、大きなイチジクの木に守られるかのように穏やかに暮らす一家。父と母と4人の子供たちの平和な暮らし。自然と人間が織りなす大きなドラマを予感させる舞台設定である。
しかし、父親のピーターが長期間にわたる仕事が終わり、が待つ自宅に戻る途中、心臓発作が原因でこの世を去ってしまう。残された妻のドーンは子どもたちを抱え、この先どうやって生きていけばいいのかわからない状態に陥っていた。そんなある日、8歳の娘シモーンが庭の大きなイチジクの木に父が宿っているのではないかと感じ、木と対話していることを知る。そんな時、新しい恋をする母親と対立するようになる。

この作品「パパの木」は、ジュリー・ベルトゥチェリにとっては「やさしい嘘」に続く長篇監督2作目。前作同様に、喪の作業が大きな柱になり、時にはユーモアを交えながら、母と娘が大自然と共に、愛する人の死を昇華していく姿が描かれていく。事実、これは、自然の力と人間の悲劇と再生と、ファンタジーと寓話に満ちた巧妙な作品になっている。撮影は見事だし、演技も充実している。わけても8歳の娘を演じるモーガナ・デイヴィーズが、あまりにも演技が達者で、母親役のシャルロット・ゲンズブールを食っているのが印象的だ。

この映画は、ジュディ・パシコーの小説が元になっているが、本作は原作よりもシャルロット・ゲンズブール演じるドーンの心理に重きが置かれているようだ。だが、この作品の中では幼い娘が父親は木の中で生きていると思いながら、父を失くした悲しみをやわらげ、そしてだんだんと父への執着を断ち切って行く。だからというわけでないが、シモーヌは一度も神の名を口にしない。今までの幾多の映画で描かれたように、神に父の復活を祈りはしない。この家族は特別な信仰を持たないという前提であったのだろう。神というものは大人が子供に教え込む存在であり、小さな子供が本能的に感じるものではないと思うから。シモーンには、神の存在より父親との交信の方が重要だったに違いない。

ですが、この木に父親が宿っていると信じることも一つの信仰だと思います。
木の精と家族の対話、彼らはそこに今は亡き父親の魂を感じ取り、日ごと、夜ごとに自分の悩みを打ち明けるのだ。
その思いが強すぎることは危険をはらんでいることも。その木がある限り父親の死を受け入れられることが出来ないのでは。死んだ人というのは、目に見えないけれども、生前以上に存在感を増すこともあるわけで、心の中に居続ける、というのは詩的だと思いますね。確か、邦画でも「桜、ふたたび加奈子」で、生まれ変わりを信じることに投影して描いていた。

木下の斜面の住居と共に、充実した画面が出現する。その存在感に負けない俳優たちも偉い。父の不在をめぐる母と娘の葛藤。母が新たな男性に近づこうとするときに、響き渡るバッハの「ヨハネ受難曲」。それはキリストの肌着の処分をクジで決めようとする兵士たちの戯れ画のようなフーガである。
ここで木がどういう手を打ってくるかが観る側の予想を超えて、嵐の夜に大音響と共に、木が倒壊するシーンに込められた深い思いには、母親のドーンも心動かされたようで。
一家が大型トラックで、トレーラーの荷台に平屋の家屋を載せて、オーストラリアの大地を移動するラストに、妙な感動を覚えた。土台から家ごと引っ越すこのカットに、どこで何が起きても家族が一体となって生きて行こうとする姿が見られる。「モーガナちゃん、ガンバレ」と、ついエールを送りたくなる自立と共生の映画ですね。
2013年劇場鑑賞作品・・・247
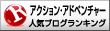 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング