「岸辺の旅」「クリーピー 偽りの隣人」の黒沢清監督が、オールフランスロケによる全編フランス語の作品に初挑戦し、キャストのみならずスタッフもほぼ全て現地で活躍する外国人を起用して撮り上げた異色のゴシック・ラブストーリー。“ダゲレオタイプ”という世界最古の写真撮影方法をモチーフに、写真家の父とモデルを務める娘、その娘を愛するアシスタントの三者が織りなす愛憎の行方を静謐かつ幻想的な筆致で描き出す。出演は「預言者」のタハール・ラヒム、「女っ気なし」のコンスタンス・ルソー、「息子のまなざし」のオリヴィエ・グルメ。
![]()
あらすじ:ジャン(タハール・ラヒム)がアシスタントとして採用されたのは、パリの古い路地に建つ屋敷にスタジオを構えるダゲレオタイプの写真家ステファン(オリヴィエ・グルメ)。その技法は、銀板に直接ポジ画像を焼き付けるため、長時間の露光が必要だった。そのため人間の被写体は、数十分にわたる露光の間、決して動くことのないよう全身を特殊な器具で拘束して撮影に臨まなければならなかった。そんな過酷なダゲレオタイプのモデルを務めていたのが、ステファンの娘マリー(コンスタンス・ルソー)だった。ジャンはその不思議な撮影方法に魅了される一方、次第にマリーに心惹かれ、父親の芸術の犠牲になっている彼女を救い出したいとの思いを募らせていくのだったが…。
![]()
<感想>黒沢清監督作品は、「岸辺の旅」「クリーピー 偽りの隣人」の2作品とも好きですね。冒頭から、青年がバイト先へ面接に訪れるところから話は始まる。玄関のソファで待っていると、背後の扉が音もなく開いたり、頭上の階段に女の姿が見えたり、気配だけがあった後、彼は雇われる。170年前に生まれた古い写真装置の、ダゲレオタイプによる撮影の助手として働くうちに、その家に幽霊が出没するのを目撃する。
幽霊の気配、写真、となればこれは堂々たる時代錯誤で語られる、黒沢清監督念願のゴシック・ホラー作品ですね。「岸辺の旅」でも亡き夫と旅行する作品でした。
青年ジャンは、古い屋敷の地下のアトリエで、露光のため被写体を拘束器具で固定する撮影が1時間以上もかかるため、巨大なカメラの前に立ったモデルのマリーの全身を奇妙な器具で固定するのである。
![]()
写真家のステファンは、マリーの父親で妻の亡霊に脅かされている。後で分かるのだが、マリーの前に妻を同じく器具で固定してモデルにして、写真を撮っていたのだが、1時間以上もの間その状態では、モデルになる女性もたまったもんじゃない。
しかし、妻は夫に言われるままに、動かぬように器具に固定され、挙句に筋弛緩剤を注射されて亡くなったのだ。そのことは、夫である写真を撮っているステファンしか知らない。彼が拳銃で自殺をした後に、最後に明かされるから。だからなのか、亡き妻の亡霊を見るようになるのだ。
![]()
それに、娘のマリーに恋をしてしまった青年ジャンも、何時間もの間器具で固定されて動けないマリーを見て、まるで拷問を受けているような感じもする。父親の写真撮影に対して文句も言わずに、ただ従っているのだが、ジャンがマリーを説得して、この老朽化した家を売却に関わるあたりから、話は劇的な展開へと突き進む。
![]()
庭にある温室で植物を育てているマリーは、遠く離れた植物園での就職が決まっている。このことが、父親とジャンの写真撮影と、くっきりと対照をなしているのだ。マリーの身体を固定する撮影が疑似的な死を思わせると共に、現像に用いた水銀の廃液が地面に零れて、植物を枯らすことになるから。そして、マリーがアトリエの階段を踏み外して転落死する。
父親は娘の死に衝撃を受け、酒に溺れてゆくのだが、ジャンはまだ彼女が生きていると信じて、車に乗せて自分のアパートで同棲をしていると妄想し、屋敷の売却作戦に乗り出す。娘のマリーは階段の下に倒れて死んだのか、生きているのか、気絶をした後に蘇生したのか。マリーが階段から足を滑らせたとは思えず、何者かに突き飛ばされたように見えたのだが。すべては定かではない。
![]()
マリーの生死が判然としないことを明確にするのは、ジャンがマリーを車に乗せて、一度後部座席からマリーが転げ落ちるのだ。慌てて、抱き上げてまたもや車の後部座席に乗せたようだが、その時、マリーは川の中へ落ちたのではなかろうか。というのも、後で、警察がその川に女性らしい死体が浮いていることを映像でにおわすから。
![]()
しかし、ジャンは自分のアパートで、マリーの亡霊と暮らしセックスまでするのだ。これはいらないと思うのだが、何せフランス映画だからなのか。屋敷はパリ郊外の再開発地区にあり、破壊と再生ということが物語の基本に設定されている。不確かさ、これがこの映画の核心であろう。
父親のステファンが撮ったマリーの等身大の写真が、印象深く出て来る。カラーなのに写真のモノクロが際立つのだが、その濃淡は実在感の希薄さを印象づける。ステファンはそれを見て、永遠の生を定着させたと確信している。
妻の亡霊をアトリエの階段の下で見たステファンは、後に全身を固定するための筋弛緩剤とわかる薬瓶を拾い、階段の上へと行き、その後にマリーが階段を上った途端に転落するのだ。
![]()
この階段は生と死の境界なのだろう。マリーと一緒に旅に出たジャンが、教会で二人っきりで結婚式を挙げ、その後に神父から声をかけられてハァっと目が覚めたように、マリーの死の事実を確認させられて哀しみつつ、亡霊と結婚式まで挙げようと思いつめていたのだろう。銀板写真家の助手の青年が経験する異常な世界の、死と愛の物語でもある。猟奇的な世界を描きながらも、確実な技術に基づいた映像美は、格調高く趣味の良さを失わない。
驚いたのは、ステファンの友人でマチュー・アマルリックが共演していることだ。
2017年劇場鑑賞作品・・・2![]() 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング/
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング/

あらすじ:ジャン(タハール・ラヒム)がアシスタントとして採用されたのは、パリの古い路地に建つ屋敷にスタジオを構えるダゲレオタイプの写真家ステファン(オリヴィエ・グルメ)。その技法は、銀板に直接ポジ画像を焼き付けるため、長時間の露光が必要だった。そのため人間の被写体は、数十分にわたる露光の間、決して動くことのないよう全身を特殊な器具で拘束して撮影に臨まなければならなかった。そんな過酷なダゲレオタイプのモデルを務めていたのが、ステファンの娘マリー(コンスタンス・ルソー)だった。ジャンはその不思議な撮影方法に魅了される一方、次第にマリーに心惹かれ、父親の芸術の犠牲になっている彼女を救い出したいとの思いを募らせていくのだったが…。

<感想>黒沢清監督作品は、「岸辺の旅」「クリーピー 偽りの隣人」の2作品とも好きですね。冒頭から、青年がバイト先へ面接に訪れるところから話は始まる。玄関のソファで待っていると、背後の扉が音もなく開いたり、頭上の階段に女の姿が見えたり、気配だけがあった後、彼は雇われる。170年前に生まれた古い写真装置の、ダゲレオタイプによる撮影の助手として働くうちに、その家に幽霊が出没するのを目撃する。
幽霊の気配、写真、となればこれは堂々たる時代錯誤で語られる、黒沢清監督念願のゴシック・ホラー作品ですね。「岸辺の旅」でも亡き夫と旅行する作品でした。
青年ジャンは、古い屋敷の地下のアトリエで、露光のため被写体を拘束器具で固定する撮影が1時間以上もかかるため、巨大なカメラの前に立ったモデルのマリーの全身を奇妙な器具で固定するのである。

写真家のステファンは、マリーの父親で妻の亡霊に脅かされている。後で分かるのだが、マリーの前に妻を同じく器具で固定してモデルにして、写真を撮っていたのだが、1時間以上もの間その状態では、モデルになる女性もたまったもんじゃない。
しかし、妻は夫に言われるままに、動かぬように器具に固定され、挙句に筋弛緩剤を注射されて亡くなったのだ。そのことは、夫である写真を撮っているステファンしか知らない。彼が拳銃で自殺をした後に、最後に明かされるから。だからなのか、亡き妻の亡霊を見るようになるのだ。

それに、娘のマリーに恋をしてしまった青年ジャンも、何時間もの間器具で固定されて動けないマリーを見て、まるで拷問を受けているような感じもする。父親の写真撮影に対して文句も言わずに、ただ従っているのだが、ジャンがマリーを説得して、この老朽化した家を売却に関わるあたりから、話は劇的な展開へと突き進む。

庭にある温室で植物を育てているマリーは、遠く離れた植物園での就職が決まっている。このことが、父親とジャンの写真撮影と、くっきりと対照をなしているのだ。マリーの身体を固定する撮影が疑似的な死を思わせると共に、現像に用いた水銀の廃液が地面に零れて、植物を枯らすことになるから。そして、マリーがアトリエの階段を踏み外して転落死する。
父親は娘の死に衝撃を受け、酒に溺れてゆくのだが、ジャンはまだ彼女が生きていると信じて、車に乗せて自分のアパートで同棲をしていると妄想し、屋敷の売却作戦に乗り出す。娘のマリーは階段の下に倒れて死んだのか、生きているのか、気絶をした後に蘇生したのか。マリーが階段から足を滑らせたとは思えず、何者かに突き飛ばされたように見えたのだが。すべては定かではない。

マリーの生死が判然としないことを明確にするのは、ジャンがマリーを車に乗せて、一度後部座席からマリーが転げ落ちるのだ。慌てて、抱き上げてまたもや車の後部座席に乗せたようだが、その時、マリーは川の中へ落ちたのではなかろうか。というのも、後で、警察がその川に女性らしい死体が浮いていることを映像でにおわすから。

しかし、ジャンは自分のアパートで、マリーの亡霊と暮らしセックスまでするのだ。これはいらないと思うのだが、何せフランス映画だからなのか。屋敷はパリ郊外の再開発地区にあり、破壊と再生ということが物語の基本に設定されている。不確かさ、これがこの映画の核心であろう。
父親のステファンが撮ったマリーの等身大の写真が、印象深く出て来る。カラーなのに写真のモノクロが際立つのだが、その濃淡は実在感の希薄さを印象づける。ステファンはそれを見て、永遠の生を定着させたと確信している。
妻の亡霊をアトリエの階段の下で見たステファンは、後に全身を固定するための筋弛緩剤とわかる薬瓶を拾い、階段の上へと行き、その後にマリーが階段を上った途端に転落するのだ。

この階段は生と死の境界なのだろう。マリーと一緒に旅に出たジャンが、教会で二人っきりで結婚式を挙げ、その後に神父から声をかけられてハァっと目が覚めたように、マリーの死の事実を確認させられて哀しみつつ、亡霊と結婚式まで挙げようと思いつめていたのだろう。銀板写真家の助手の青年が経験する異常な世界の、死と愛の物語でもある。猟奇的な世界を描きながらも、確実な技術に基づいた映像美は、格調高く趣味の良さを失わない。
驚いたのは、ステファンの友人でマチュー・アマルリックが共演していることだ。
2017年劇場鑑賞作品・・・2
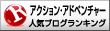 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング/
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング/