『冬の小鳥』のウニー・ルコント監督がメガホンを取り、親を知らずに育ったヒロインと母親の30年振りの再会を描くヒューマンドラマ。出生の秘密を調べるため、とある町に引っ越した理学療法士が、運命的な再会を果たすさまを映し出す。主演は、『君と歩く世界』などのセリーヌ・サレット。治療を通して共鳴し合う娘と母の心と共に、ジャン=リュック・ゴダール作品などの撮影を手掛けてきたカロリーヌ・シャンプティエによる叙情的な映像も胸にしみる。
あらすじ:生みの親が誰かわからない理学療法士のエリザ(セリーヌ・サレット)は、自分の出生について調べようと息子と一緒に北フランスのダンケルクに移り住む。しかし、実母は匿名を望んでいた。ある日、息子が通う学校に勤務しているアネット(アンヌ・ブノワ)が、エリザの療法室を訪れる。治療を重ねるにつれて、二人は不思議な親密感を覚え……。
![]()
<感想>韓国の孤児院を舞台に、里親を待つ子供たちと過ごす9歳のジニの“通過儀礼”を描いた『冬の小鳥』(09)に感動しつつ、今回もウニー・ルコント監督の生い立ちを反映した、孤児の女性の母親探しの物語。原題は、アンドレ・ブルトン「狂気の愛」の末尾の一言。これだったら、邦題の付け方の優しい感じがいい。
観ていてあの「冬の小鳥」のあの孤児院の少女が、この映画の監督なのだと言う思いが頭から離れなかった。確かに、前作「冬の小鳥」のタッチと繊細さと頑固さが共存しており、さりげなく動くカメラも悪くはない。
![]()
理学療法士であるヒロインは、情報よりも先に、直接その探していた母親の肌に触れるという手掛かりを得るが、漂う予感が確信に変わるまでの不確かさが美しく感じた。
エリザは母親を知りませんが、母親の肉体から生まれたのです。その出産という極めて肉体的な行為を想起させるような、手と肌と骨の映像が観ているこちらにも伝わってくるようでした。だから、エリザが施術をする時の肌の描写が、息をのむほどに美しかった。
![]()
この物語は、子供を捨てた母親と養父母の元で育った子供、その二人の30年後の姿、再会を描きたいということから始まっている。その内にお互いが親子と知らない段階で、既に再会していたらどうなるのだろう。
自分探しというのは嫌いな言葉ですが、生みの親を知りたいと思うことは、自分を知りたいことに他ならない。監督が韓国の孤児院で育ち、9歳で養女となりフランスへと渡ったルコント監督の切実なテーマであります。
![]()
エリザが息子を連れて自分が育った養護施設を訪ねるけれども、塀に阻まれて中には入れないという、痛切な光景が映し出される。子供を養子にだした母親が匿名を希望する場合には、それぞれの事情があると思います。しかし、子供が自分を探していると知って名前を公表するのは、果たして誰のためなのだろうか。知りたい子供、知りたい親、さらには知らせたいという親の想いが加われば、当事者同士の望むところは合致するはずなのに。理屈どうりにはいかないところが、逆に真実味があるのです。
![]()
そしてエリザを生んだ母親のアネットが、匿名を解除して実名を名乗るために書類に書くシーンがあります。1981年11月17日にダンケルクの産院で女児を出産。エリザベットと命名。彼女はその後は、結婚していないようで、現在は小学校の給食のおばさんと、掃除の仕事をしている。合間に近所の犬の散歩も。その小学校で、エリザの息子のノエと出会い、孫が宗教上の理由から豚肉を食べられないという、その時の給食は豚のソーセイジでした。転校生でもあり、他の子供たちかた虐められているような感じもしました。
![]()
それに、息子の父親とは別居生活という、エリザのお腹には彼の子供が宿っており、自分のルーツのこともあり彼の2人目の子供を産みたくないという選択をします。そういう意味のあってなのか、彼女が自分の生い立ちを知りたくなって、母親の住んでいる場所へと引っ越してきたのでしょう。結局は、彼女の判断で2人目の子供は中絶してしまう。この迷いも女性には、大変精神的にも肉体的にも辛い選択だったと思います。
エリザは確信を得て、生みの母親であるアネットのところへ。そこには兄妹と住んでいる母親の幸せそうな姿がありました。自分の出生の秘密を知り、本当はこんな理由だったなんて知らなくても、孤児院で育った子供には、親が自分で育てる力がないという理由が多いのに。
![]()
自分が里親のところで幸せに暮らし結婚もして、息子を生み、それに第二子まで授かったのに。自分の出生の事実を知ったことで、何が変わると言うのか。他人の生き方にあまり苦言は言いたくないが、もっとしっかりと足を地に付けて生きて欲しかった。息子は母親の生き方を良く見ているから。
もっとドラマチックに描かれるところを、抑制が効いており良かった。あまり私には好きなタイプの映画ではないが、こういう母娘ものは、日本では受けるのだろう。最後の朗読は唐突でもあるが、これを言いたかったのだと思う。
2016年劇場鑑賞作品・・・195![]() 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング
あらすじ:生みの親が誰かわからない理学療法士のエリザ(セリーヌ・サレット)は、自分の出生について調べようと息子と一緒に北フランスのダンケルクに移り住む。しかし、実母は匿名を望んでいた。ある日、息子が通う学校に勤務しているアネット(アンヌ・ブノワ)が、エリザの療法室を訪れる。治療を重ねるにつれて、二人は不思議な親密感を覚え……。

<感想>韓国の孤児院を舞台に、里親を待つ子供たちと過ごす9歳のジニの“通過儀礼”を描いた『冬の小鳥』(09)に感動しつつ、今回もウニー・ルコント監督の生い立ちを反映した、孤児の女性の母親探しの物語。原題は、アンドレ・ブルトン「狂気の愛」の末尾の一言。これだったら、邦題の付け方の優しい感じがいい。
観ていてあの「冬の小鳥」のあの孤児院の少女が、この映画の監督なのだと言う思いが頭から離れなかった。確かに、前作「冬の小鳥」のタッチと繊細さと頑固さが共存しており、さりげなく動くカメラも悪くはない。

理学療法士であるヒロインは、情報よりも先に、直接その探していた母親の肌に触れるという手掛かりを得るが、漂う予感が確信に変わるまでの不確かさが美しく感じた。
エリザは母親を知りませんが、母親の肉体から生まれたのです。その出産という極めて肉体的な行為を想起させるような、手と肌と骨の映像が観ているこちらにも伝わってくるようでした。だから、エリザが施術をする時の肌の描写が、息をのむほどに美しかった。

この物語は、子供を捨てた母親と養父母の元で育った子供、その二人の30年後の姿、再会を描きたいということから始まっている。その内にお互いが親子と知らない段階で、既に再会していたらどうなるのだろう。
自分探しというのは嫌いな言葉ですが、生みの親を知りたいと思うことは、自分を知りたいことに他ならない。監督が韓国の孤児院で育ち、9歳で養女となりフランスへと渡ったルコント監督の切実なテーマであります。

エリザが息子を連れて自分が育った養護施設を訪ねるけれども、塀に阻まれて中には入れないという、痛切な光景が映し出される。子供を養子にだした母親が匿名を希望する場合には、それぞれの事情があると思います。しかし、子供が自分を探していると知って名前を公表するのは、果たして誰のためなのだろうか。知りたい子供、知りたい親、さらには知らせたいという親の想いが加われば、当事者同士の望むところは合致するはずなのに。理屈どうりにはいかないところが、逆に真実味があるのです。

そしてエリザを生んだ母親のアネットが、匿名を解除して実名を名乗るために書類に書くシーンがあります。1981年11月17日にダンケルクの産院で女児を出産。エリザベットと命名。彼女はその後は、結婚していないようで、現在は小学校の給食のおばさんと、掃除の仕事をしている。合間に近所の犬の散歩も。その小学校で、エリザの息子のノエと出会い、孫が宗教上の理由から豚肉を食べられないという、その時の給食は豚のソーセイジでした。転校生でもあり、他の子供たちかた虐められているような感じもしました。

それに、息子の父親とは別居生活という、エリザのお腹には彼の子供が宿っており、自分のルーツのこともあり彼の2人目の子供を産みたくないという選択をします。そういう意味のあってなのか、彼女が自分の生い立ちを知りたくなって、母親の住んでいる場所へと引っ越してきたのでしょう。結局は、彼女の判断で2人目の子供は中絶してしまう。この迷いも女性には、大変精神的にも肉体的にも辛い選択だったと思います。
エリザは確信を得て、生みの母親であるアネットのところへ。そこには兄妹と住んでいる母親の幸せそうな姿がありました。自分の出生の秘密を知り、本当はこんな理由だったなんて知らなくても、孤児院で育った子供には、親が自分で育てる力がないという理由が多いのに。

自分が里親のところで幸せに暮らし結婚もして、息子を生み、それに第二子まで授かったのに。自分の出生の事実を知ったことで、何が変わると言うのか。他人の生き方にあまり苦言は言いたくないが、もっとしっかりと足を地に付けて生きて欲しかった。息子は母親の生き方を良く見ているから。
もっとドラマチックに描かれるところを、抑制が効いており良かった。あまり私には好きなタイプの映画ではないが、こういう母娘ものは、日本では受けるのだろう。最後の朗読は唐突でもあるが、これを言いたかったのだと思う。
2016年劇場鑑賞作品・・・195
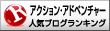 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング