日本でもロングランとなった「木洩れ日の家で」で2008年サンフランシスコ国際映画祭観客賞ほか多数の賞に輝いたポーランドの名匠ドロタ・ケンジェジャフスカ監督が、詩情豊かに描く子どもたちの旅。
![]()
旧ソ連の貧しい村に生きる家も身寄りもない3人の少年が、今よりもいい暮らしを夢見て国境を越える旅に出る姿を追う。製作・撮影監督は「トリスタンとイゾルデ」のアルトゥル・ラインハルト。「ウィニングチケット −遥かなるブダペスト−」「ニキフォル −知られざる天才画家の肖像−」などの名作を日本に紹介した丹羽高史らが共同製作として参加。第61回ベルリン国際映画祭ジェネレーション部門グランプリおよび平和映画賞受賞作品。
あらすじ:ポーランドにほど近い旧ソ連(ロシア)のとある貧しい村。親も住む家もない幼い3人の少年は、生きるために物乞いや盗みを働き、駅舎で夜を過ごしていた。3人は、外国へ行けばきっと今よりもいい暮らしができるとの希望を胸に、越境の旅に出る。危険の多い命がけの旅を乗り越えて3人はポーランドの田舎町にたどり着くが……。 (作品資料より)
![]()
<感想>冒頭で駅の構内を走り回る少年たち、夜になると駅のベンチの下に段ボールを敷き、そこで眠る子供たち。その子供たち3人が、何故か隣の国ポーランドへ逃避行という物語。
国境線は見えない。見えないけれど厳然と存在して、ここと向こうを分けている。向こうはポーランド、ここは旧ソ連(現在のロシア)の寒村だ。パスポートどころか戸籍さえあやしい6歳、10歳、11歳の孤児たち。はっきり言えば浮浪児トリオは、物乞いとかっぱらいで何とか命を繋いでいる。もちろん学校は縁がないから読み書きさえおぼつかない。年長の子が「国境の向こう、すぐそこには、ここよりいい暮らしがある」と固く信じて踏み出した旅。
![]()
貨物列車のタダ乗り、農家の納屋泊まり、親切なトラックの荷台便乗などを重ねて辿り着いた国境は、何重もの有刺鉄線柵と監視所に守られている。深夜、3人は、空き缶をシャベルにして柵の下を掘って潜り抜け、一番怖い電線の有刺鉄線を潜り抜け、水を渡り、やっとの思いで辿り着いたポーランドの警察に、言葉もろくに通じないのに保護願いをする。
デブで中年の警察署長も同情はするものの、歴然とした密入国者を“ハイそんならご自由に何処へでも“と解放するわけにはいかない。最高の親切は彼らをもと来たところへ送り返すだけ。
ここで電話の内容で語られる「亡命」という言葉を知らないばかりに、ロシア側の警察へと引き渡される。ほろ苦いだの挫折だのなんてものではない。少年たちの冒険はすべて徒労に終わり、命の危険さえあった行動が無に帰るのだ。前回「木漏れ日の家で」(07)が不思議な感銘を与えてくれた女性監督ドロタ・ケンジェジャフスカの新作は、家族連れで観るには辛いものがあると思う。
![]()
例えば署長が見逃してくれるとか、孤児院への取り次ぎをしてくれるとか、思わぬ引き取り手が現れるとかのありがちなんてゼロなのが、いかにもポーランド映画らしい。
それにしてもポーランドの女性たちの描き方が酷い。
![]()
幼いペチャの可愛いこと、その子供にお世辞を言われて、露天商のパン売りのおばさんがパンをくれる。それに途中で教会で結婚式をあげた車を止めて、子供なのに一緒に酒を飲み、花嫁にペチャが綺麗だといい、お腹が大きい花嫁を見てきっと男の子だと褒める。気を良くしてお金を上げる花嫁。そして、警察の受付嬢のなんて仕事をしてるのかどうか、色気をふりまくケバイ化粧の女である。
道端で言葉が分からない異国の地で、子供らに馬鹿にされ、そこにいた幼い女の子がパンを手に持っている。その子が同情してかどうか知らないが、警察にパンを持って現れるのが不思議な感じがした。
少年たちに同行取材したドキュメンタリーのような展開と描写。彼らが出会うさまざまな職業の人や、様々な暮らしで国境地帯に生きる人生を垣間見せた上で、国境というものの実感をもたずに、呑気に暮らす私たちが決して味わえない緊張感を、しばしながら体験させてくれる。
2013年劇場鑑賞作品・・・58![]() 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキングへ
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキングへ

旧ソ連の貧しい村に生きる家も身寄りもない3人の少年が、今よりもいい暮らしを夢見て国境を越える旅に出る姿を追う。製作・撮影監督は「トリスタンとイゾルデ」のアルトゥル・ラインハルト。「ウィニングチケット −遥かなるブダペスト−」「ニキフォル −知られざる天才画家の肖像−」などの名作を日本に紹介した丹羽高史らが共同製作として参加。第61回ベルリン国際映画祭ジェネレーション部門グランプリおよび平和映画賞受賞作品。
あらすじ:ポーランドにほど近い旧ソ連(ロシア)のとある貧しい村。親も住む家もない幼い3人の少年は、生きるために物乞いや盗みを働き、駅舎で夜を過ごしていた。3人は、外国へ行けばきっと今よりもいい暮らしができるとの希望を胸に、越境の旅に出る。危険の多い命がけの旅を乗り越えて3人はポーランドの田舎町にたどり着くが……。 (作品資料より)

<感想>冒頭で駅の構内を走り回る少年たち、夜になると駅のベンチの下に段ボールを敷き、そこで眠る子供たち。その子供たち3人が、何故か隣の国ポーランドへ逃避行という物語。
国境線は見えない。見えないけれど厳然と存在して、ここと向こうを分けている。向こうはポーランド、ここは旧ソ連(現在のロシア)の寒村だ。パスポートどころか戸籍さえあやしい6歳、10歳、11歳の孤児たち。はっきり言えば浮浪児トリオは、物乞いとかっぱらいで何とか命を繋いでいる。もちろん学校は縁がないから読み書きさえおぼつかない。年長の子が「国境の向こう、すぐそこには、ここよりいい暮らしがある」と固く信じて踏み出した旅。

貨物列車のタダ乗り、農家の納屋泊まり、親切なトラックの荷台便乗などを重ねて辿り着いた国境は、何重もの有刺鉄線柵と監視所に守られている。深夜、3人は、空き缶をシャベルにして柵の下を掘って潜り抜け、一番怖い電線の有刺鉄線を潜り抜け、水を渡り、やっとの思いで辿り着いたポーランドの警察に、言葉もろくに通じないのに保護願いをする。
デブで中年の警察署長も同情はするものの、歴然とした密入国者を“ハイそんならご自由に何処へでも“と解放するわけにはいかない。最高の親切は彼らをもと来たところへ送り返すだけ。
ここで電話の内容で語られる「亡命」という言葉を知らないばかりに、ロシア側の警察へと引き渡される。ほろ苦いだの挫折だのなんてものではない。少年たちの冒険はすべて徒労に終わり、命の危険さえあった行動が無に帰るのだ。前回「木漏れ日の家で」(07)が不思議な感銘を与えてくれた女性監督ドロタ・ケンジェジャフスカの新作は、家族連れで観るには辛いものがあると思う。

例えば署長が見逃してくれるとか、孤児院への取り次ぎをしてくれるとか、思わぬ引き取り手が現れるとかのありがちなんてゼロなのが、いかにもポーランド映画らしい。
それにしてもポーランドの女性たちの描き方が酷い。

幼いペチャの可愛いこと、その子供にお世辞を言われて、露天商のパン売りのおばさんがパンをくれる。それに途中で教会で結婚式をあげた車を止めて、子供なのに一緒に酒を飲み、花嫁にペチャが綺麗だといい、お腹が大きい花嫁を見てきっと男の子だと褒める。気を良くしてお金を上げる花嫁。そして、警察の受付嬢のなんて仕事をしてるのかどうか、色気をふりまくケバイ化粧の女である。
道端で言葉が分からない異国の地で、子供らに馬鹿にされ、そこにいた幼い女の子がパンを手に持っている。その子が同情してかどうか知らないが、警察にパンを持って現れるのが不思議な感じがした。
少年たちに同行取材したドキュメンタリーのような展開と描写。彼らが出会うさまざまな職業の人や、様々な暮らしで国境地帯に生きる人生を垣間見せた上で、国境というものの実感をもたずに、呑気に暮らす私たちが決して味わえない緊張感を、しばしながら体験させてくれる。
2013年劇場鑑賞作品・・・58
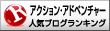 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキングへ
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキングへ