1960年代のポーランドを舞台に若い修道女が出生の秘密をたどる旅を描き、トロント国際映画祭など各映画祭で好評を博したヒューマンドラマ。自分がユダヤ人であることを告げられたヒロインが、両親の死の真相を知るべく過去をひもといてゆくさまをつづる。監督は『マイ・サマー・オブ・ラブ』『イリュージョン』などでメガホンを取り、本作で初めて母国で作品を手掛けたパヴェウ・パヴリコフスキ。モノクロで表現される美しい映像もさることながら、ヒロインの過去を通して触れられるユダヤ人やホロコーストの歴史にも胸を打たれる。
![]()
<感想>前から気になって観たいと思っていました。ミニシアターにて観賞。この映画は白黒であり、台詞も説明も極力排除した作り方は、この上なくストイックな感じでした。ポーランド人のユダヤ人に対する罪責感を主題にしている。以前見た、ロマン・ポランスキー監督の「戦場のピアニスト」で描かれたように、ポーランド人はワルシャワにいたユダヤ人の、対独蜂起を支援せず見殺しにした。ポーランド各地で同じようなことが起きて、戦後それがポーランド人の汚点となり、罪の意識になっている。
![]()
見習いの尼僧アンナ=イーダを演じるアガタ・チュシェブホフスカの初々しさがいつまでも脳裏に残る。彼女が実はユダヤ人だったということが、物語の大きなポイントになっているようだが、それがどれほどのことなのか。戦争孤児として育ち、修道女である立場を含めて、感情をあらわにしない、できないイーダというキャラクターの演出にもこの美学は貫かれていると思う。
その対極に生きる者のように登場する彼女の叔母は、検察官でアルコール中毒で、正義や感情に振り回され、強さも弱さも兼ね備えたとても人間的な人物だが、イーダと二人で共有する過去の秘密を知るためのロードムービーと見る事も出来る。二人が最後にどのような運命を辿るかというところに、この映画の意志が現れているようだ。
どこか不安感が漂う、そしてリアルなモノクロームの雪の中のシーンから始まるこの映画は、この二人の心象が解けかかったり、少しずつ凍結し始めたり、画面自体が呼吸しているように見えた。
![]()
やがて、イーダは戦時中に父母が住んでいた家へと、さらなるルーツ探しの旅へと。途中で叔母の言う「美人ね、えくぼがいい、ほら笑うとできる」そのこと言葉でイーダの口元がほころぶ。しかし、イーダは赴いた先で出自にまつわる歴史の現実に向かい合うことになる。
イーダを連れて、両親が殺されたという寒村に旅する。自分たちは、ユダヤ人でありそして、ポーランド人に迫害されたと、辛い過去を話して聞かせる。ポーランド人の村人から、イーダの両親が、さらには叔母の小さな男の子までもが、どのように殺されたかを知ることになる。
どんなにおぞましいこと、恐ろしいことを知ろうとも、イーダはじっと口を結んで受け止める。そして祈りを捧げる。五十年以上も前の過去が、いまもポーランド人にとって深い傷になって残っているのだ。
![]()
しかし無表情で受け止めきれるものだろうか。口を結んだ修道女たちが居並ぶ中で、イーダの口元が遂に崩れる。笑いが噴出す。イーダがサックス吹きの青年とベランダで横に並び、そのままの位置で微笑みを交わしたシーンの後で、僧服の帽子を取り上着を脱ぐ画面になる。これは青年とのセックスの続く暗示あるいは象徴なのだろうか。自分の部屋に戻ってリラックスして自分を見つめるシーンなのか、どう理解していいのか分からなかった。
この映画の中で繰り返しかけられる「ジュピター」交響曲の居心地の悪さは何に起因するのか。決定的な場面で「ジュピター」が流れる。叔母のヴァンダが、少し引いた画面の中でレコードに針を落とし、画面から居なくなってレコードの終わるころに登場して、また針を落とし直して開いた窓から外へと、飛び降りて自殺してしまう。自分の子供が無惨に殺されたと知り、その衝撃に耐えられずに。
![]()
最後、イーダは叔母の葬儀を終え、旅の途中で知り合った青年と夜を共にしたあと、修道院へと帰る。自らの手で人生を選び直し、歩き出すイーダの姿が神々しくさえ感じた。
何よりもモノクロで、スタンダードという画面に釘付けになりました。それと、白い雪の中の修道院、聖像、納屋に取り付けられた手作りのステンドガラス、さびれた村など、映像の美しさが一番の見所と言っていいのではないか。
2014年劇場鑑賞作品・・・317![]() 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング

<感想>前から気になって観たいと思っていました。ミニシアターにて観賞。この映画は白黒であり、台詞も説明も極力排除した作り方は、この上なくストイックな感じでした。ポーランド人のユダヤ人に対する罪責感を主題にしている。以前見た、ロマン・ポランスキー監督の「戦場のピアニスト」で描かれたように、ポーランド人はワルシャワにいたユダヤ人の、対独蜂起を支援せず見殺しにした。ポーランド各地で同じようなことが起きて、戦後それがポーランド人の汚点となり、罪の意識になっている。

見習いの尼僧アンナ=イーダを演じるアガタ・チュシェブホフスカの初々しさがいつまでも脳裏に残る。彼女が実はユダヤ人だったということが、物語の大きなポイントになっているようだが、それがどれほどのことなのか。戦争孤児として育ち、修道女である立場を含めて、感情をあらわにしない、できないイーダというキャラクターの演出にもこの美学は貫かれていると思う。
その対極に生きる者のように登場する彼女の叔母は、検察官でアルコール中毒で、正義や感情に振り回され、強さも弱さも兼ね備えたとても人間的な人物だが、イーダと二人で共有する過去の秘密を知るためのロードムービーと見る事も出来る。二人が最後にどのような運命を辿るかというところに、この映画の意志が現れているようだ。
どこか不安感が漂う、そしてリアルなモノクロームの雪の中のシーンから始まるこの映画は、この二人の心象が解けかかったり、少しずつ凍結し始めたり、画面自体が呼吸しているように見えた。

やがて、イーダは戦時中に父母が住んでいた家へと、さらなるルーツ探しの旅へと。途中で叔母の言う「美人ね、えくぼがいい、ほら笑うとできる」そのこと言葉でイーダの口元がほころぶ。しかし、イーダは赴いた先で出自にまつわる歴史の現実に向かい合うことになる。
イーダを連れて、両親が殺されたという寒村に旅する。自分たちは、ユダヤ人でありそして、ポーランド人に迫害されたと、辛い過去を話して聞かせる。ポーランド人の村人から、イーダの両親が、さらには叔母の小さな男の子までもが、どのように殺されたかを知ることになる。
どんなにおぞましいこと、恐ろしいことを知ろうとも、イーダはじっと口を結んで受け止める。そして祈りを捧げる。五十年以上も前の過去が、いまもポーランド人にとって深い傷になって残っているのだ。

しかし無表情で受け止めきれるものだろうか。口を結んだ修道女たちが居並ぶ中で、イーダの口元が遂に崩れる。笑いが噴出す。イーダがサックス吹きの青年とベランダで横に並び、そのままの位置で微笑みを交わしたシーンの後で、僧服の帽子を取り上着を脱ぐ画面になる。これは青年とのセックスの続く暗示あるいは象徴なのだろうか。自分の部屋に戻ってリラックスして自分を見つめるシーンなのか、どう理解していいのか分からなかった。
この映画の中で繰り返しかけられる「ジュピター」交響曲の居心地の悪さは何に起因するのか。決定的な場面で「ジュピター」が流れる。叔母のヴァンダが、少し引いた画面の中でレコードに針を落とし、画面から居なくなってレコードの終わるころに登場して、また針を落とし直して開いた窓から外へと、飛び降りて自殺してしまう。自分の子供が無惨に殺されたと知り、その衝撃に耐えられずに。

最後、イーダは叔母の葬儀を終え、旅の途中で知り合った青年と夜を共にしたあと、修道院へと帰る。自らの手で人生を選び直し、歩き出すイーダの姿が神々しくさえ感じた。
何よりもモノクロで、スタンダードという画面に釘付けになりました。それと、白い雪の中の修道院、聖像、納屋に取り付けられた手作りのステンドガラス、さびれた村など、映像の美しさが一番の見所と言っていいのではないか。
2014年劇場鑑賞作品・・・317
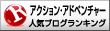 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング